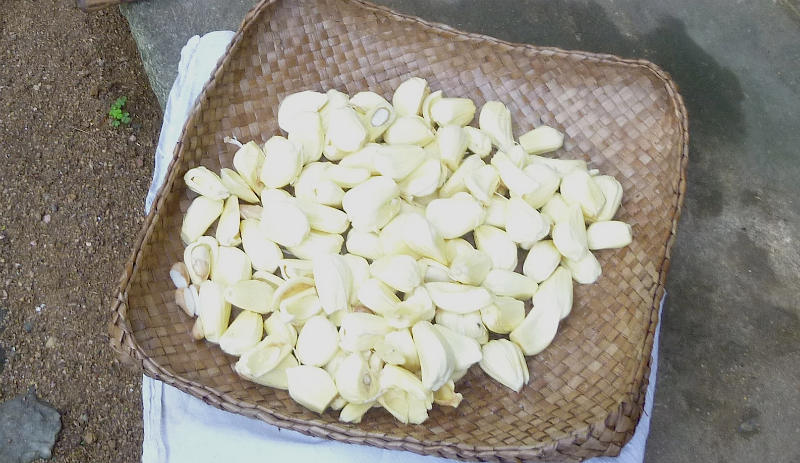スリランカ南端の街「マータラ」に行って来ました!
ここは2004年、はじめてスリランカを訪れた時に滞在して以来、だいたい足を運ぶ街。ジャヤさんとその家族、そしてその親戚のみんながいるスリランカでの古里のような場所。
今回もお世話になりました。
 ジャヤさん。長女ラクナディ、次女ソナディ、奥にいるのが初対面の長男アケーン。
ジャヤさん。長女ラクナディ、次女ソナディ、奥にいるのが初対面の長男アケーン。
(スリーウィーラーに7名で乗車中)
 家にはいつも近所の子供がいっぱい。
家にはいつも近所の子供がいっぱい。

リアル井戸端会議。 2時間経過。
マータラはけっこう大きな街。

そして、ちょっと街を離れると

ミーハラカー(水牛)いっぱいの田んぼ広がるカントリーサイド。
(ジャヤさん家近く)
少し行ったスリランカ最南端の岬、デウンダラ港の朝の魚市場の活気は凄い!
でっかい魚いっぱい。
マータラ。
五日間の滞在、本当にたくさんの料理をみんなで作りました!!
デウンダラ港での買った魚達。  大きい魚の身は、
大きい魚の身は、
黒胡椒ペーストとゴラカペーストと合わせて。

大きい魚の頭は


フィッシュヘッドカレー(ココナッツミルク版)に!ええ出汁でとる。
インディアーッパと一緒に!
小魚は、

フライに!
パパダン、ポロス(若いジャックフルーツ)、パリップ(レンズ豆)、カンクン(空心菜)
赤いお米はスリランカ南部でよく食べられる「ラトゥキャクル」。
他にも、
野菜イロイロうまい。
 こちらはゴトゥコラ。
こちらはゴトゥコラ。

ルーヌマル。直訳すると「玉ねぎの花」

右からルーヌマルテルダーラ(炒め物)、ゴトゥコラサンボーラ(和え物)、アラホディ(ジャガイモの汁カレー)、アンブルティヤル。

右から。
コヒラダルの炒め物。キリコス(ジャックフルーツのココナッツミルクカレー)。オムレット(スパイス入の卵焼)。小魚のフライ(衣なし版)

右から、コヒラ・サンボーラ、ナスのカレー、パリップ、パパダン 、ゆで卵。

右からコス・マッルン(ジャックフルーツのさっと煮)、アンブルティヤル、パトーラ(蛇瓜)とジャガイモの汁カレー、コスアタ(ジャックフルーツの種)、パパダン。
他にも朝飯にパーン!

スリランカでは食パンをよく食べます!「パーン」。
食べ方↓

左手でパーンをキープ。右手で千切って、汁を浸して頬張ります!
ちなみに写真の汁のカレーは、カラワラ(干し魚)とジャガイモのココナッツミルクカレー。茶色のはビリンという実の炒め物。
ビリンはこんな実↓
 酸っぱくて良し!
酸っぱくて良し!
ブリヤーニにも挑戦。


ククルマス(チキン)ブリヤーニ。
カジュ(カシューナッツ)のカレーとチリペーストで。
ヌードルスも。

しっかり辛いチキンカレーとジャガイモのカレーとチリペースト。
ホンマにいっぱい作って、いっぱい食うたー!!
そんで、マータラでの〆は基本これ。

キリパニ。
ミーキリ(水牛のヨーグルト)にキトゥルパニ(孔雀椰子の花蜜)をかけたもの。酸味が強めで濃厚なミーキリ&少しスモーキーで甘さすっきりのキトゥルパニは相性抜群!スリランカ南部の名物で、素焼きの土の鉢が丸いのはマータラスタイル。
旨いもん腹一杯食べて、田舎道プラプラして、田んぼに沈む夕日拝めば、
オッコマ・ハリ!!(ALL OK!!)